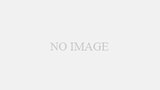駅の改札とネット上の仮想通貨、近くて遠い関係
あなたが駅で Suica のカードをタッチして改札を通るとき、そのカードには「いくらチャージされていて」「どこで何回使ったか」という記録が刻まれています。これは“電子マネー”として私たちの日常に非常に溶け込んでいる仕組みです。一方で、最近よく耳にする Bitcoin(ビットコイン)をはじめとする“暗号通貨”も、「お金を電子的に動かせる」という意味では似ているように感じます。でも、実際には「Suica」と「ビットコイン」では、発行される仕組み・管理される主体・使われ方など、かなり異なるところがあるのです。今回はこの“電子マネー”と“暗号通貨”を、「Suicaとビットコイン」という身近な例で比較しながら、音楽活動をするあなたの視点からも共感できるように解説していきます。
電子マネーとは何か?
まず「電子マネー(e-マネー)」について軽く整理しましょう。電子マネーとは、現金の代わりに、あらかじめチャージされたり銀行口座から紐付けされたりして、電子的に決済できるお金の形式のことです。Suica や PASMO といった交通系ICカード、あるいはスマホ決済アプリの残高などが典型例です。
このタイプのお金は、多くの場合 国・地域の法定通貨(例えば日本なら円)を電子的に表したもの で、「円」という信頼できる通貨を基礎にしています。また、発行・管理にはその国の銀行やカード会社などの 中央管理者(あるいは許可を受けた事業者) が関わっています。
このように、電子マネーは「法定通貨を裏付けに」「管理者がいて」「チャージ・決済を電子的に」という形で、私たちの日常に溶け込んでいます。さらに、取引履歴の管理や残高の把握がシステム上で行えるため、私たちは “駅で改札を抜ける/コンビニでタッチして支払う” といった体験をスムーズに行えているわけです。
暗号通貨とは何か?
では、暗号通貨とはどのようなものか。代表格のビットコインを例にとると、暗号通貨とは『暗号技術を用いてネットワーク上で取引・記録がなされ、中央の発行者や管理者に必ずしも依存しないお金・トークン』のこと、という定義が多く見られます。例えば、オーストラリアの中央銀行の解説では、「暗号通貨は立法上の法定通貨ではなく、人々が市場で支払う意志によって価値を持つ」ものだと説明されています。
特徴的なのは、暗号通貨は「分散型ネットワーク」「ブロックチェーン」という技術によって、取引の履歴が改ざんしづらく(過去記事参照)なっており、かつ「中央の銀行や政府が発行量を自由に変更できない(またはその設計になっている)ものもある」という点です。
そして、「世界中どこからでもアクセスできる」「銀行口座がなくても取引できる可能性がある」「価値が上下しやすい(投機対象になりやすい)」という特徴も併せ持ちます。
Suica(電子マネー)とビットコイン(暗号通貨)を並べて考える
ここで、私たちが「Suicaで改札を通る体験」「ビットコインで支払うまたは送る体験」を対比してみましょう。
- 発行・管理者の違い
Suica は、鉄道会社や交通系サービスの会社(中央管理者)がチャージや利用履歴を管理しています。
一方、ビットコインは特定の会社が発行・管理しているわけではなく、ネットワーク上の多数のコンピュータ(ノード)が取引記録を分散して保有・検証する仕組みです。 gemini.com+1 - 裏付けとなる価値・法的な位置づけの違い
Suica にチャージされた「円」は、法定通貨である「円」を電子化したものであり、国や政府が“この通貨は信用できますよ”と保証しています。
対してビットコインは、国家が法的に「支払い義務を果たせます」という法定通貨とは異なり、市場参加者が価値を認めて使うことで価値を持っています。 - 利用範囲・目的の違い
Suica は主に国内の交通や日常の小売り支払いに使われ、支払い・チャージという“支払い手段”として非常に実用的です。
ビットコインは支払い手段として使われることもありますが、むしろ「投資対象」「価値保存手段」「国際送金の手段」としての側面が強く、「日常コンビニでSuicaよろしく使えるか」というと、まだ限定的です。 - 価格の安定性・変動の違い
Suica 残高=日本円ということで、価格変動のリスクがほとんどありません(為替・インフレなど別の話ですが、利用時に「今日はSuica残高が半分になった」ということはありません)。
ビットコインは、その価値が需要・供給・投機・規制ニュースなどによって大きく上下することがあります(=ボラティリティが高い)という特徴があります。 - 取引の検証・仕組みの違い
Suica の決済は、カード会社・交通会社・システム事業者などが中央で承認・記録をしています。
ビットコインでは、誰でも参加できるノードがブロックチェーン上に記録を分散させていて、取引承認は多数のノードの合意(コンセンサス)によってなされます。これが “銀行を通さず、ピアツーピアでやり取りできる” という設計の根底にあるわけです。 gemini.com+1
音楽活動との接点で考えるなら
音楽の練習や活動においても、「誰がいつ練習したか」「どの楽譜を使ったか」「どんな録音を残したか」といった“記録”を共有・管理することがあります。ここで、電子マネーと暗号通貨の違いを、音楽活動の視点でひとひねりしてみましょう。
電子マネー=Suica のような支払い使いやすさ・信頼・安定がある仕組みを、音楽で例えるなら「合奏のための定期的な練習時間記録」や「講師への支払いをいつも通り同じ流れで行う」ような、信頼された定型の仕組みです。
暗号通貨=ビットコインのような仕組みを、音楽で例えるなら「オンラインで世界中の演奏家と新しい練習記録を共有・投票で決める」「録音の権利をブロックチェーン上で管理して誰が使っても良いという条件をあらかじめプログラムする」など、新たな可能性を探る実験場とも言えます。
つまり、電子マネーは「安心・既存の枠組み」で動く日常インフラ的な存在、暗号通貨は「新しい枠組み・挑戦的な設計」で動く未来志向的な存在と言えます。
まとめと次への意欲
この記事では、電子マネーと暗号通貨という一見似たようで異なる仕組みを、「Suicaとビットコイン」という身近な例を通じて整理しました。発行者・価値の裏付け・使い道・構造といった観点から見ると、電子マネーは「法定通貨を裏付けとし、中央管理者のもとで利用される」、暗号通貨は「暗号技術と分散型ネットワークを使い、中央管理者に依存しない可能性を持つ」といった違いがあります。
音楽活動に例えてみると、電子マネーは「定番・安定感ある練習基盤」、暗号通貨は「新たに挑むプラットフォーム」というイメージです。次回は、そんな暗号通貨を支える”ウォレット”について、「自分の楽器を選ぶような感覚」で見ていきたいと思います。音楽とテクノロジーが交わる地点で、私たちは新しい演奏・共有・創造の形を描けるはずです。どうぞ楽しみにお待ちください。