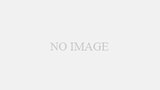なじみの“記録”から考える
楽譜を前にして、「この楽譜が誰かによって改ざんできないようになったらいいな」と思ったことはありませんか?あるいは、日記をつけていて、「この日記を誰かがこっそり書き換えたらイヤだな」と感じたことは?実は、そんな「記録/履歴を安全に残す仕組み」をインターネット上で実現しようとする技術が、いま多く注目されている ブロックチェーン(blockchain)です。今回は、その“日常の記録”に例えて、ブロックチェーンとはそもそも何か、なぜ注目されているのか、という点を演奏者・活動者の視点も交えて丁寧に紐解いてみましょう。
日常の記録とブロックチェーンの対比
まず、「記録」という言葉を少し掘り下げてみます。例えば、あなたが練習ログを手書きでつけたとします。「今日は30分スケール練習、次に曲を通した」など。これを“台帳”と考えると、紙の台帳はあなた個人が管理していて、隠してもいいし、書き直しても誰も気づかないこともあります。では、これを楽譜を含めた“誰でも見られる台帳”にするとどうなるか?たとえばクラスの全員が「今日の練習時間」を共有し、みんなで同じ台帳を持っていて、誰かが「今日10分しかやってません」と書き換えたら、他の人が「いや、30分書いてたよ」と気づく…そんな感覚です。
ブロックチェーンも、まさにこの「みんなが“同じ記録”を共有して改ざんしにくくしておこう」という発想から出てきています。専門的には「分散型台帳技術(Distributed Ledger Technology, DLT)」とも呼ばれ、複数のノード(参加者の端末・コンピュータ)で“台帳”を一斉に管理し、改ざんが極めて難しい構造になっています。
もっと具体的に言うと、ブロックチェーンは「ブロック(記録の塊)」が「チェーン(鎖:連結)」となって積み重ねられる構造を持っています。たとえば「ブロックA」があって「ブロックB」が続き、「B」は「A」の情報を基にしている…という形です。この構造があるため、もし誰かが “昔のブロック”をこっそり書き換えると、その先のチェーン全体が不整合になってしまい、ネットワーク参加者が「おかしい」と気づくことが可能なのです。
では、「楽譜や日記」の観点からもう少し掘り下げましょう。あなたが演奏会に向けて、クラス全員で「練習時間」を共有する記録を持つとします。「誰がいつどれくらいやったか」だけでなく、「誰がどこのパート練習したか」「練習後にどう感じたか」なども書いてあるかもしれません。もしこの記録が「全員が閲覧できて、かつ誰も勝手に書き替えできない」仕組みなら、クラスの一体感も高まるし、「あ、私だけ練習が足りてないかも」と気づくきっかけにもなります。
ブロックチェーンも似た役割を、インターネット上の“記録”に対して果たします。たとえば、ある仮想通貨の取引履歴をブロックチェーンに記録すれば、「いつ誰がどれだけ送ったか」が透明に残り、かつ変更できません。また、「誰が責任をとるの?」という問いに対して、「中央の管理者(銀行やサーバー)ではなく、みんなで支え合う構造だよ」という設計になっているのが特徴です。
さらに、「この仕組みがどう動くのか」を、もっと演奏・合奏の感覚で例えてみます。想像してみてください。「みんなで歌って録音しよう」という合唱の練習風景。各パート(ソプラノ、アルト、テノール、バス)がそれぞれ練習記録を残して、最後に「今日は何分何を練習しました」「次回までにこの部分をこう直します」と報告。これを“ブロック”と考えます。その後、次の練習でまた記録をとって報告、…このように“ブロック”が次々に継承されていき、「連続した履歴」ができあがっていきます。もし誰かが「昨日30分練習した」と書き換えたら、他の人が「あれ?その記録が直前の報告と矛盾してるよ」と気づける、そんなイメージです。これが「改ざんが難しい連続構造」という点のアナロジーになります。
また、なぜ“チェーン”つまり「つながり」が重要なのかというと、次のように整理できます。単に“記録を一つ残す”だけなら、紙の日記でも十分ですよね。でも、「その記録が過去からつながっていて、誰がいつどんな変化をしたかが連続的に見える」ようになっていると、複数人で運営する記録としての価値がさらに高まります。ブロックチェーンはまさに、その「履歴の連続性」と「多数参与による共有」という二つを兼ね備えているわけです。 (Simplilearn.com)
そして、私たち音楽活動で言えば、「この曲のこの部分を練習しました→次回までにこう直します」という履歴がしっかり残っていて、しかも「誰かがこっそり“この日はやりました”とだけ書いた」というのが見抜けると、練習効率・信頼感ともに上がります。ブロックチェーンの世界でも、「この取引があった/この記録が登録された」という信頼の仕組みを、中央管理者を介さずに構築することが目指されているのです。
まとめ:音楽活動視点でとらえる価値と次のステップ
振り返ると、ブロックチェーンとは「みんなで共有する台帳」「改ざんしにくい記録」「履歴のつながり(チェーン)」といった特徴を持つ技術です。そして、私たちの音楽活動にも似た“記録を共有・蓄積する”という体験があるため、そのイメージを使うことで少し身近に感じられるのではないでしょうか。
もちろん、実際にはブロックチェーンは仮想通貨だけでなく、サプライチェーン(物の流れ)や著作権管理といったさまざま応用分野を持っています。しかしまずは「何がどう記録されていて、どうして“チェーン”になるのか」「なぜ中央管理者がいないで信頼できるのか」という基礎を押さえておくことで、次のテーマ(例えば「暗号通貨と電子マネーの違い」など)もスムーズに理解できるようになります。
次回は、“電子マネー”と“暗号通貨”はどう違うのか?”という視点で、「日常のSuicaとビットコインを並べて考える」記事を書きたいと思います。演奏・練習の世界と同じように、一歩ずつ記録を重ね、理解を深めていきましょう。では、また次回もよろしくお願いします。