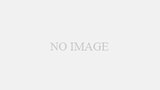はじめに
「もう少しちゃんと仮想通貨の世界に入ってみよう」――そんな思いから、私がまず手を付けたのが“ウォレット作成”でした。仮想通貨を買ったり送ったりする前に、自分のデジタル財布をしっかり用意しておきたい。今回は、3つのサービス、MetaMask、bitFlyer、KuCoinを使って、それぞれウォレットを立ち上げた体験を記録します。初心者にとっての「小さな成功体験+手順+注意点」を中心に、お伝えします。
実践・手順と感想
MetaMaskでの作成
まずは自分で鍵を握るタイプのウォレット、MetaMask。Webブラウザ拡張やスマホアプリで使え、いわゆる“非カストディアル(自分が鍵を管理する)”の代表格です。公式ガイドでは、インストール → 「Create a Wallet」選択 → パスワード設定 → シードフレーズ(バックアップ用12~24語)を保存という流れが紹介されています。 (nft now)
実際私も Chrome の拡張機能としてインストール。初めに「ウォレットを新規作成」ボタンを押した時、ちょっと胸が高鳴りました。というのも、シードフレーズを吐き出す瞬間、「本当に自分が鍵を持つんだ」という実感が湧いたからです。メモ用紙に書いて、紙フォルダに入れておきました。
ただし気をつけたこともあります。
- シードフレーズは絶対にネット上(スクリーンショット、テキストファイル)に残さない。ガイドにも「オフライン保存を強く推奨」されていました。 (nft now)
- パスワードは「拡張機能/アプリを開くための鍵」であって、シードフレーズそのものではない。紛らわしいので理解しておきました。 (codehs.com)
- ネットワーク(Ethereum/BSC/Polygon等)を後で追加できる余地があることを知って、初期設定だけ済ませて先に進みました。 (CoinGecko)
この MetaMask作業を終えた時には、「自分専用のウォレット」が手元に出来た実感があり、次に進む勇気がわきました。
bitFlyerでのウォレット作成(口座+ウォレット)
次に、国内の主要取引所、bitFlyerを利用してウォレット機能を持つ口座を作りました。実際には「取引所アカウント作成 → ウォレット機能利用」といった流れです。公式サイトでは、メール登録 → 二段階認証設定 → 個人情報登録・本人確認という流れが紹介されています。 (bitFlyer)
また、「ウォレット」という用語についても、「ビットコインアドレスなど、プライベートキーを管理する自分のアドレス」という説明がありました。(bitFlyer)
私の場合、メール登録までスムーズに終え、2FA(Google Authenticator)も設定。本人確認書類の撮影が少し緊張しましたが、数時間後に承認されて、JPY入金・暗号通貨購入が可能になる状態に。
ウォレット機能を使う上で注意したのは、「出金/送金先アドレスの登録」が必要だという点。例えば、外部ウォレットへ送金する際には、アドレスを登録し、メールの確認リンクをクリックして完了という流れが公式に説明されていました。(bitFlyer)
この段階で、「交換所型ウォレット(=取引所が鍵を預かるタイプ)」を持ったという安心感と同時に、「自分で鍵を管理するわけではない」という理解も芽生えました。
KuCoinでのウォレット作成
最後に、グローバルな取引所、KuCoinで“Web3ウォレット”を作ってみました。公式ブログでは「アプリ内で Web3 → 『Create New Wallet』をタップ。シードフレーズが即生成される」という説明があります。(KuCoin)
この「Web3ウォレット」というのは、自分で鍵を持つ非カストディアルタイプなので、MetaMaskに近い感覚でした。アプリをスマホに入れて、「新しいウォレットを作成」→ パスワード設定 → シードフレーズ保存 → 確認というステップでした。
印象としては、海外サービスらしくUIが少し専門的という印象もありましたが、英語・日本語どちらも対応しており、それほど迷いませんでした。注意した点として、「日本居住者対応」「法規制や出金条件」が取引所によって異なる可能性あり、後から調べることにしました。(ウィキペディア)
この3つを自分で一通り作ったことで、「取引所ウォレット/自分鍵ウォレット」の違いや、鍵の管理ということについて、体感を伴って学ぶことができました。
まとめ
今回の「初めてのウォレット作成」は、自分の中で“仮想通貨を始める第一歩”として非常に価値ある体験になりました。MetaMaskで自分の鍵を持つ感覚を得、bitFlyerで国内取引所型のウォレットを体験し、KuCoinでグローバルなWeb3ウォレットにも触れました。
それぞれに共通して感じたのは「鍵・シードフレーズ・アドレス」の管理が、資産を安全に保つ鍵(まさに)であるということ。そして、「送金・取引は取り消せない」というブロックチェーンの性質ゆえの責任感。
次回は、実際に少額を送金してみる「送金体験」を予定しています(表に挙げたNo.14)。今回のウォレット作成体験を土台に、さらに一歩進んで、実践を増やしていきたいと思います。読んでくださった皆さまも、自分なりのウォレット作成を通して感じたことがあれば、ぜひ共有してみてください。次回も一緒に、少しずつ前へ進んでいきましょう。